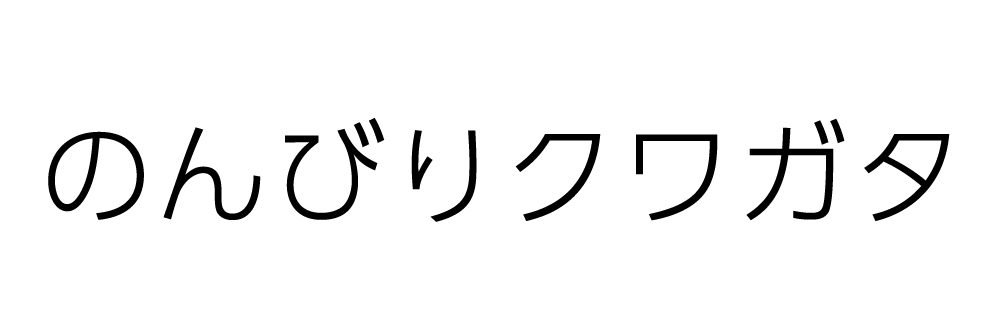崎陽軒のおいしさは、ある秋、彼が教えてくれた
◇

◇
僕が瓢さんと出会ったのは、秋の日のことだった。
校庭の鉄棒はしんとつめたく、吹き抜ける風は僕の耳たぶを冷やしている。
霧掛かった空気はどこまでも続いて、真っ白な曇り空と繋がっていた。

家に帰ると、テーブルの上にはお母さんが買っておいてくれた崎陽軒のシウマイがあった。
シウマイの小さな箱を手に取って、電子レンジに入れようとしたときだった。
「待てよ」
不思議な声がした。
おじさんみたいな声だったような気もするし、お兄さんみたいな声だった気もする。
急に僕の前に現れた不思議な人。
いや、普通の生きた人ではないんだろうけど。
いつも瓢箪(ひょうたん)でお酒を飲んでいるその人は、どう考えても人間ではなかったけど、確かに僕のお兄さんであり、先生だった。
いつからか僕はその人を「瓢さん」と呼んでいた。
瓢箪型のとっくりでお酒を飲んでいたから僕がそう名付けたような気もするし、もともと名前を知っていたような気もする。
それでも、確かにあの秋、僕はその人を「瓢さん」と呼んでいた。
◇

◇
「温めなくていい」
瓢さんはそう言った。
ぶっきらぼうな言い方にも、優しい口調にも聞こえた。
「そうなの?」
「崎陽軒のシウマイは冷めても旨いんだよ。駅弁だからな。冷めた状態でおいしくなるように作ってある。」
「わかった」
しんとした室温よりも少しだけ冷たく感じるシウマイを、僕はそのまま口に運んだ。
「おいしい!!!」
思わず声を上げた。
瓢さんは満足げに笑っている。
不思議な存在が現れた奇妙さが、今になって実感を帯びてきた。
「おじさん、崎陽軒の人なの?」
僕の質問がおかしかったのか、瓢さんは小さく吹き出すように笑って言った。
「ガキにはわかんねえよ」
◇

◇
ある日学校から帰ると、テーブルの上にはお母さんが買っておいてくれた崎陽軒のシウマイがあった。
―温めなくていいんだよな。

僕は包みを開け、一口大のシウマイを口に運んだ。
確かに、冷めていてもおいしい。
すぐに次のシウマイを頬張った。
おいしい。
いや、むしろ冷めているからこその味わいなのかもしれない。
次の一口に手を伸ばしたそのとき、部屋に小さく声が響いた。
「早い」
瓢さんだとすぐにわかった。
瓢さんはいつも僕の前に急に現れて、いつの間にか消えていた。
「崎陽軒のシウマイは、味わいが長いんだ。そんなにポンポン食っちまうもんじゃねえよ。」
「長い?」
「いいから、ゆっくりよく噛んで長く味わってみろ。」
僕は、瓢さんが言うように、ゆっくりと、よく味わってみた。
「どうだ?何の味がする?」
噛めば噛むほどに、じんわりと強い旨味が口の中に広がる。
大好きな豚肉の旨味と、いやな尖りのない玉ねぎの柔らかい甘味。
……それだけじゃない。
これは何だろう?
豚肉だけじゃない。
確かに知っている味だ。
この味は…。
「…ホタテ?」
そう答えると、瓢さんは驚いたように笑った。
「お前、よくわかったな!」
僕は瓢さんが褒めてくれたのがうれしかった。
「崎陽軒のシウマイはな、ホタテの干し貝柱が使われている。じっくり味わってっとよくわかんだろ。」
瓢さんは相変わらずの喋り方だけど、どこかうれしそうなのは僕にもわかった。
◇

◇
ある日家に帰ると、テーブルの上にはお母さんが買っておいてくれた崎陽軒のシウマイがあった。
お母さんはけっこう崎陽軒のシウマイを買ってきてくれる。

僕はだいぶ崎陽軒のことがわかってきた。
“通”というやつかもしれない。
「調子乗るのは早えぞ坊主」
瓢さんだ。

「醤油付けねえのが偉いとでも思ってんだろ」
「そんなことない!」
「ガキが好んで薄味にするわけねえんだよ」
「うるさい!!!」
瓢さんは、たまにすごく嫌なことを言ってくる。
僕は醤油をつけずに、そのままシウマイを食べた。
ほら、おいしいじゃん。
僕は、瓢さんにばかにされたのが嫌だったんじゃない。
たぶん、言い当てられてしまったのが悔しかったんだ。
◇

◇
翌日だったと思う。
僕は、醤油をかけてみることにした。

醤油を垂らすと、一気に景色が華やいで見えた。
シウマイに醤油をかけて食べるのはすごく久々な気がした。
僕はそれを、放り込むように口に運んだ。
「うまいか?」
瓢さんだ。
「うん。」
「悪かったな。」
「大丈夫。やっぱり醤油かけてもおいしい。」
「そうか。」
瓢さんは、またうれしそうにしていた。
僕は、通ぶりたかった気持ちに自分で気づいてしまうのが怖かったんだと思う。
瓢さんと仲直りして食べたシウマイは、いつもよりゆっくりと味を感じることができた。
胸の下のあたりからふわっと力が抜けたような感触を、今でも覚えている。
初めて醤油をかけずにシウマイを食べたときよりも、自分が大人になれたような気がした。
◇

◇
ある日家に帰ると、テーブルの上にはお母さんが買っておいてくれた崎陽軒のシウマイがあった。
お母さんは、僕を異常なシウマイ好きだと思い込んでいるんだろう。
こんど訂正しておこう。

今日も醤油をかけて食べてみる。
「うまいか?」
瓢さんはいつも、うまいかどうかを聞いてくる。
「うん、うまいよ」
「醤油をかけないのとどっちが好きだ?」
「うーん、かけた方が好きかなあ」
そう答えながら、どこか引っかかるものがあった。
もう一度、ゆっくりと味わって食べてみる。
――かぐわしい醤油の香り。
塩気も舌に残り、シウマイの味わいを引き立てる。
けれど、味わっているうちにやがてそれらは薄れていき、あとに残るのは、あのじんわりとした旨味だった。
豚肉、玉ねぎ、そして干し貝柱―。
そうか!
醤油をかけても、その味のあとには必ず素のシウマイの味わいが残る。
つまり、醤油をかけて食べれば、醤油ありと醤油なしの両方食べたのと同じなんだ!
醤油ありは、醤油なしの完全上位互換!
「本当にそうか?」
満足そうな顔のまま、瓢さんはまた僕に問いかけた。
聞かれている意味は、あんまりわからなかった。
僕は、瓢さんがいるこの日々が長くは続かないことは、なんとなくわかっていた。
◇

◇
ある日家に帰ると、テーブルの上にはお母さんが買っておいてくれた崎陽軒のシウマイがまたあった。
いよいよマジで買いすぎだ。
僕は嬉しいけど、食育とかの観点でどうなんだろう。
――ずっと無視してきた。
見て見ぬふりをしてきた。
シウマイには、からしがついてくる。
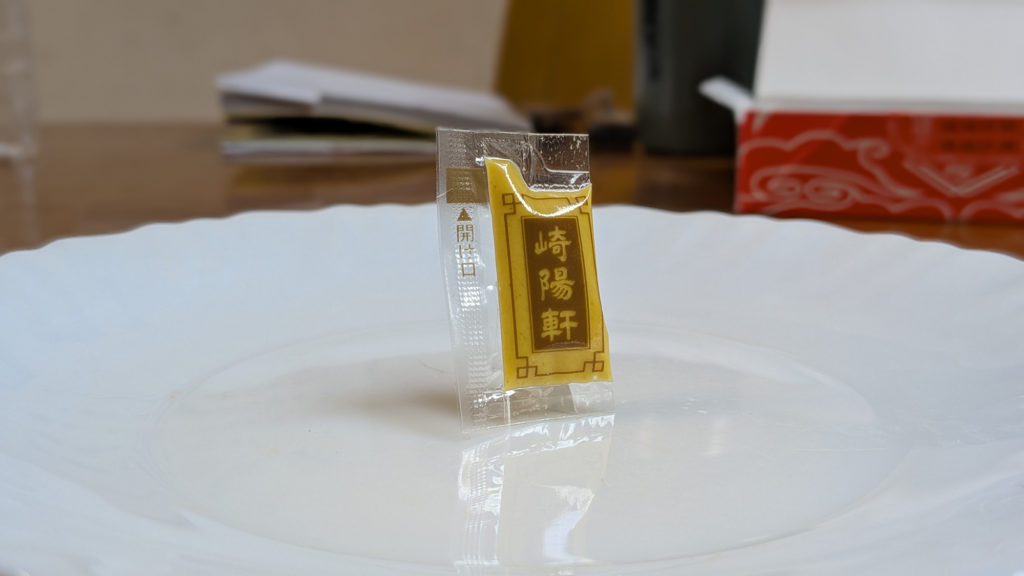
辛いのは苦手だ。
お寿司も、いつもサビ抜きを頼んでいる。
大人にならなくちゃ、とずっと思ってきた。
サビ抜きはかっこ悪いから。
大人と同じものを当たり前に食べられるほうがかっこいいから。
でも、それよりも、シウマイのことを知りたい。
崎陽軒のシウマイを理解したいという気持ちで、僕はからしをつけてみることにした。

つんとした刺激が鼻の奥に抜ける。
僕はびっくりして、口と鼻を手のひらでまとめて覆った。
その直後、鋭い刺激が去ると、豊かなからしの風味と一緒にシウマイの旨味が広がった。
僕はこのとき、シウマイがわかったような気がした。
「うまいか?」
いつの間にか瓢さんは隣にいた。
「…うまい」
大人になったような誇らしい気持ちを悟られないように、できるだけ落ち着いてそう言った。
瓢さんもうれしそうに笑っていた。
「これがシウマイの完全体だね。」
僕は瓢さんにそう言った。
からしをおいしいと思えたことを、瓢さんにわかってほしかったんだと思う。
瓢さんは笑った顔のまま、何も言わなかった。
けれど、その横顔は、僕にはよくわからない、少しだけ遠いところを見ているような気がした。
◇

◇
ある日家に帰ると、テーブルの上にはお母さんが買っておいてくれた崎陽軒のシウマイがまたあった。
お母さんは、僕のことを本当に異常シウマイ愛好者だと思い込んでいるのだろう。
前は訂正しようと思ったこともあったけど、このままでいいような気がしてきた。

崎陽軒のシウマイ。
冷えたままでおいしい。

醤油もかける。

からしもつける。
醤油とからしは、口に入れた瞬間にふわっと広がって、シウマイを彩ってくれる。
そして、やがてどんどん醤油もからしもかけないシウマイの素の味に近づいてくる。
そのまま長く味わっていると、豚肉、干し貝柱、玉ねぎなど、複雑な味の集まりを感じ取ることができる。
これが、シウマイの完全体。
…なのだろうか?
完全体? 本当に?
――瓢さんは何と言うだろうか。
瓢さんは現れなかった。
やっぱり。
瓢さんがもう現れないことは、僕はなんとなくわかっていた。
なんとなく思っていたことが現実になり、部屋は静かで、どこからも返事はなかった。
僕はひとりで考えるしかなかった。
初めて瓢さんと会ったときのシウマイを思い出す。
確か、僕がシウマイを温めようとして、止められて―

――そのまま食べたんだ。
醤油もつけずに。
あの美味しさは何にも代えられない。

――そうか。
醤油もからしも、どっちもつけたっていい。
ゆっくりと長く味わっていれば、シウマイを余すことなく楽しめる。
そのまま食べたっていい。
口に入れた瞬間からゆっくりと広がるシウマイの味。
それを楽しむのも自由だ。
そう、「自由」だ。自分が食べたいように食べればいい。
シウマイは自由なんだ。
好きに食べていい。
自分で楽しみ方を見つけていくことがシウマイなんだ。
僕は、自分でたどりついたこの答えを一人で何度も反芻した。
この答えに気づけた僕を、誰よりも瓢さんに知ってほしかったのに。
◇
その日、改札を入ると、冷たい風が駅の階段をすり抜けていった。
ポケットの中に振動を感じ取ると、指先が無意識に通知をタップしている。
部内の進捗報告に目を通しながらも、頭では既に来月の決算資料の段取りを考えていた。
ネクタイの結び目を少し直しながら、同じように急ぐ人波に身をゆだねる。
そのとき、視界の端にひとつのポスターが飛び込んできた。

――あれ…?

胸の奥で、何かが微かにざわめいた。
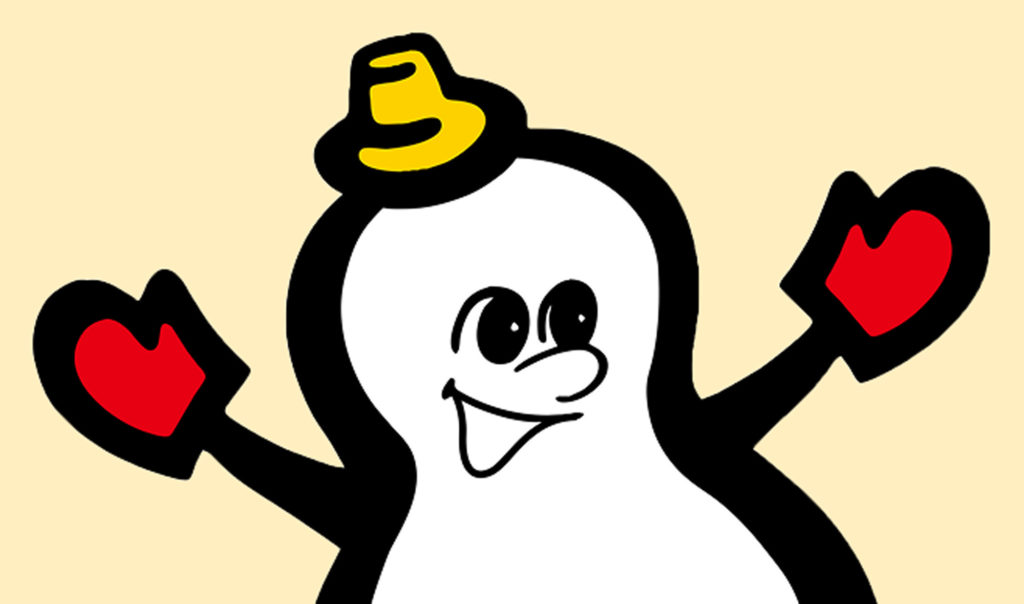
何か大事なことを、誰かとの思い出を、置き去りにしてきてしまった気がする。
忘れてはいけないことを、忘れてしまった気がする。

しかし、その「誰か」のことは、もう思い出せなかった。
ただ、言葉にならない空白だけが残った。
…
人波の流れに急かされ、はっと我に返り、歩き出す。
――最近あんまり買ってなかったな。
崎陽軒のシウマイは息子の大好物だ。
忙しさもあって気が回らず、最近はあまり買ってやれてなかった。
久しぶりに買って帰って、一緒に食べるか。

最寄り駅の階段を登って地上へ出ると、空高くまで冷えたような秋夜の空気がコートの襟元に流れ込んだ。
ビルの間を抜けていく風は、やけに軽く丸まった枯葉をころころと転がしていた。